 
第3話(その2)
ヴィストゥール要塞は「バルディアスの門」より三・六光年を隔てたエトール恒星系の小惑星帯にある。エトール恒星系には七つの惑星が存在し、小惑星帯はその第三惑星と第四惑星の公転軌道の中間地点に輪になって帯のように連なっている。そこに軍事上の目的で建設されたヴィストゥール要塞は、複数の小惑星を内部をくりぬいてつなぎあわせた簡単な作りのものであるが、最大で二○○○隻近い艦隊を収容可能な規模を誇っていた。常時、ここには二五○隻からなる半個艦隊が駐留していた。
アルフリート率いるクレティナス軍第四九艦隊がこの要塞に補給と作戦準備のために立ち寄ったのは、宇宙標準暦一五六三年一月四日、王都星フェリザールを発ってから二週間目のことであった。
「何度来てみても、あいかわらず殺風景なところだなあ。ヴィストゥールは」
要塞に上陸して最初に発したファン・ラープの言葉には深いため息が混じっていた。流れ星作戦を前にしてせっかく艦隊司令官アルフリートが将兵全員に一二時間の自由行動を許してくれたというのに、ヴィストゥール要塞には何もなかったのである。
「一二時間もいったい何をしてひまをつぶせばいいんだ。遊ぶところもなければ女もいない。おまけに飲酒は制限つきだ。これじゃあ、仕事をしていたほうがよっぽどましじゃないか」
ファンは落胆せずにはいられなかった。おかげで、普段の彼には似合わないことを口走っている。他の者に聞かれたら笑いの種にされること間違いなしの台詞である。
「では、ファンだけ休みを取り消しにしてやろうか」
背後から声がしてファンは振り向いた。そして次の瞬間、彼は顔を引きつらせていた。眼前に意地の悪い視線を投げかけているアルフリートと必死に笑いをこらえるベルソリック准将の姿があったのである。
「いえ、……遠慮させていただきます」
「何だ、労働意欲が湧いてきたんじゃないのか。残念だなあ」
アルフリートの皮肉にも似た言葉がファンの太い神経に突き刺さった。
「残念ですなあ。私もたまには真面目に働くラープ提督の姿を見たかったんですが」
さらに追い打ちをかけるようにベルソリックが続いた。
「二人ともやめてくださいよ」
ファンは身を小さくして抗議の声をあげた。
アルフリートとベルソリックはそれを見て大きな声で笑っていた。
「そんなことよりどうしたんです、二人とも。そんな格好をしてどこかに出かけるんですか」
二人の宇宙服姿に気が付いたファンは気をとりなおして尋ねた。アルフリートとベルソリックはファイターやアースムーバーのパイロットが身につける機能性の高いスペーススーツに身を包んでいたのである。
「宇宙だ。これから例の物を見に行こうと思ってな。ヴィストゥールは何もないところだが、外の小惑星帯はなかなか面白いらしい。散歩のついでに見てこようとベルソリック准将を誘ったんだ」
「ずるいですね。二人だけで楽しむなんて。私は誘ってくれないのですか」
「働き者のラープ准将は休みより仕事の方が好きだと思ってな。散歩なんかに誘ったら悪かろう」
「いえいえ、そんなことはありませんよ。普段の私を一番知っているのは閣下ではないですか」
ファンは自分から不真面目さを認めて応えていた。普段仕事をさぼっていることには何の罪悪も感じない彼なのである。そんなファンに対してアルフリートは苦笑するしかなかった。
「仕方ない。連れていくとしよう」
ヴィストゥール要塞外部の宙域には、直径二○キロを越えるものだけでも数千個の小惑星が点在していた。最大のものでは直径二○○○キロもあり、惑星と言ってもおかしくないほどの大きさがあった。また小惑星帯の平均的な密度は一立方センチあたり二・七六グラムで、構成する主成分はFeケイ酸塩と鉄、ニッケル、マグネシウムなどの金属物質であった。
アルフリート、ファン、ベルソリックの三人は練習用のアースムーバーにそれぞれが乗り込んで小惑星帯を遊覧していた。特別にパイロットを頼むことなく、自ら操縦レバーを握っての飛行である。小さい氷の破片や宇宙塵を避けながらの操縦はスリルがあり、普段戦艦に乗って艦隊の指揮を執る彼らにとっては、少なからぬ興奮を味わうことができた。「要塞『バルディアスの門』は『ウルド・ベルダンディ・スクルド』という三つの球状の要塞から成り立っているんだ。一つ一つの大きさは直径四○キロを越えていて、それぞれに強力な要塞砲が備え付けられている。要塞の装甲はビームを反射するぶ厚い金属で覆われていて、戦艦の主砲くらいでは破壊できない。また、要塞には神将と呼ばれるタイラーの艦隊一四○○隻があって、防衛にあたっている。それを通常の攻撃で破壊することはほとんど不可能と言えるだろうな」
流れ星作戦のための作業が行なわれている一つの小惑星を前にして、アルフリートは語りだした。直径二○キロ、質量一兆トン以上、平均密度一立方センチあたり二・九九グラムの巨大な小惑星である。天体と言ってもおかしくないそれには、現在何千人もの要塞の作業員がついて作業を続けていた。
「この要塞を破壊する手段としては二種類の方法が考えられる。一つは要塞の内部に侵入し爆弾などによって要塞のコアを破壊する方法、もう一つは要塞の防御能力を上回る攻撃を外部から加える方法だ。そこで、私は二段階による破壊作戦を考えた」
操縦席の左右のスクリーンパネルにはファン、ベルソリックの顔が映し出されている。アルフリートの視線は彼らではなくメインスクリーンに映る小惑星に向けられていた。
「第一段階はすでに話したと思うが、あの小惑星を使う作戦だ。小惑星は全部で三個用意されているが、それぞれに建設中の要塞の移動などに使われている六基の推進装置が備え付けられている。それを『バルディアスの門』まで運んで三つの要塞に衝突させるんだ。これだけのものをもらっては無敵の要塞もひとたまりもあるまい」
「そうですね。考えるほうも考えるほうですが」
ファンはつぶやき、脳裏にアルフリートの恐い顔を思い浮かべていた。
「第二段階は第一段階が失敗したときに発動させる作戦だ。これは先にも言ったように、外部からの攻撃がだめなら内部からというものだ。あらかじめ用意した帝国軍の艦艇にこちらの工作員を乗せて混戦のなか要塞内に侵入させる。そして、要塞のエネルギー制御システムを破壊して融合炉の暴走を引き起こし、要塞そのものを爆破する。まあ、こんなものだ。おそらく、こちらの作戦は使わずに済むと思うが」
「なるほど」
ベルソリックはうなずいた。
「ところで、順調に作業が進んであと何日くらいかかるんです?」
ヴィストゥール要塞が嫌いなファンが尋ねた。
「一週間と言ったところかな。そのあとの推進装置の試験運転がまだ四・五日くらいかかけど、二週間以内には出撃できると思うよ」
「ええ!まだ二週間もあるんですか」
ファンは嘆いた。
アルフリート達の乗る三機のアースムーバーは、流れ星作戦に使う小惑星から再び距離を置こうとしていた。小惑星帯のなかをベテランパイロット顔負けのスピードで移動する。アルフリートはアースムーバーの操縦は下級士官時代以来久しぶりのことだったが、その技術にはファンやベルソリックも驚かされるものがあった。
小惑星帯には、小惑星を構成する金属鉄の固まり以外にも、宇宙塵や事故で難破した宇宙船の残骸等が数多く散らばっている。中には、ほとんど無傷のまま小惑星に挟まれて動けなくなった宇宙戦艦もあった。三機のアースムーバーは、まるで船の墓場のように残骸が散在する宙域まで進んで前進を止めた。
「話は変わるが君たちは『ラグナロック』という言葉を聞いたことがあるかい」
破壊の後のような光景を目にしてアルフリートは尋ねた。
「我ら人類の故郷、地球の神話ですか」
「そう、北欧神話だ。それに出てくる言葉で『神々の黄昏』を意味するらしい」
「美しい響きの言葉ですね」
ファンが似合わない言葉を言った。
「ああ。しかし、内容は恐ろしいものさ。この世の滅亡を意味しているんだからね。善なる神々と邪神たちの引き起こした世界戦争、その戦いの末に世界のすべてを支える宇宙樹イグドラシルが枯れて、世界は滅んだという。……何となく今の世の中に似ている気がしないかい」
アルフリートは目を閉じて、じっと思いをめぐらしていた。
「クレティナスが善なる神々で、千年帝国が邪神たちということですか」
「いや、どちらがいいとか悪いとかじゃないんだ。私が言いたいのは、巨大な二つの勢力のぶつかり合いの果てに来る世界のことさ。神話では二つの勢力はともに滅亡している。共倒れさ」
「………」
「興味深いことに『バルディアスの門』を構成する三つの要塞は北欧神話にちなんで名前がつけられている。『ウルド』は過去、『ベルダンディ』は現在、『スクルド』は未来を意味する人間の運命を司る三人の姉妹神の名だ。神話のなかでは世界を支えるイグドラシル(宇宙樹)の番をしている。我々はその三姉妹を破壊しようと言うんだ。面白いと思わないかい。我々は彼女たちを倒してラグナロックを引き起こそうとしているんだからね」
アルフリートの話のなかに危険なものを感じたのはベルソリックだけではなかった。いつにはなくファン・ラープも厳しい表情をしている。アルフリートは確かに名将と言われるだけの能力をもっていたが、どこかしら軍人という範囲ではとらえきれないところが存在していた。
「つまり、閣下はこのまま戦争を続ければ、クレティナスも帝国も滅ぶとおっしゃるのですか」
「永久不滅の国家なんてあるわけがないだろう」
アルフリートの声には冷たいものがあった。
「そう思いながらも閣下は戦おうとなされる。どういうことでしょうか?」
ベルソリックの問いに対してアルフリートは沈黙していた。帝国が滅ぼうがクレティナスが滅ぼうが彼には関係なかったのである。彼にとっては、両者とも失われた歴史を取り戻すために倒さなくてはならない敵であった。
「未来は誰にも予測できないものさ。それに私は、これから何が起きるかではなくて、何かをしようと考える方がずっと建設的だと思うね」
しばらくの間を置いてのアルフリートの返答は、ベルソリックの期待するものとは違っていたが、彼にも理解できるところであった。
未だに、アルフリートの真意を知る者は、この銀河にはひとりもいない。彼が何を目指し、何をしようとしているのか、腹心を自称するファンでさえも知らなかった。アルフリートが、千年もの長きにわたって続いた貴族による支配体制を変革し、失われた人類の歴史を取り戻そうとしていることなど。
人は戦いに目的を持って臨んでいるのだろうか。アルフリートは考えるのだった。国家を指導する立場の人間は確かに何かしらの目的を持っているものだ。しかし、その下で手足のごとく使われている将兵達は、はたして自分の戦う理由を知っているのだろうか。
|
 |
  |
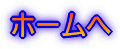
|

